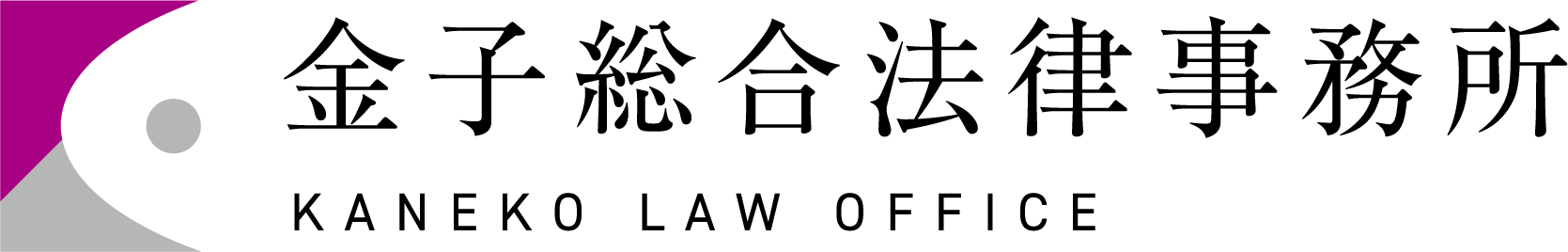本判決の内容(抜粋)
- 最高裁昭和37年9月4日第三小法廷判決
本件は、被上告人らが上告人の不法行為によりこうむった損害の賠償債務の履行およびこの債務の履行遅滞による損害金として昭和三一年一月二二日以降年五分の割合による金員の支払を求める訴訟であることが記録上明らかである。そして、右賠償債務は、損害の発生と同時に、なんらの催告を要することなく、遅滞に陥るものと解するのが相当である。
前提知識と簡単な解説
金製債務の遅滞の責任
金銭債務の不履行による損害賠償金を「遅延損害金」といいます。遅延損害金の額は、法定利率によります(民法419条1項本文)。ただし、法定利率を超える約定利率が定められているときは、約定利率によることとなります(民法419条1項ただし書)。
債権者が遅延損害金を請求するには損害の証明をすることを要せず、債務者は不可抗力をもって支払を拒むことはできません(民法419条2項)。
遅延損害金が発生するのは、履行遅滞となった時からです。履行遅滞となる時期は、(a) 確定期限のある債務については、その期限の到来した時(民法412条1項)、(b) 不確定期限のある債務については、債務者が期限の到来を知った時(民法412条2項)、(c) 期限の定めのない債務については、債務者が履行の請求を受けた時(民法412条3項)とされています。
本判決の意義
本件では、不法行為に基づく損害賠償債務の遅滞の時期が問題となりました。この点につき、大審院判例は、「債務者は債務の発生すると同時に履行の責あるを以て特に債権者の請求を待たずして遅滞の責に任ずべき」とし(大審院明治43年10月20日判決)、不法行為成立時から遅延損害金が発生するとの立場を採っていました。
本判決は、先例に従って不法行為成立時説に立つことを明らかにしたものと考えられています(枡田文郎『最高裁判所判例解説』)。