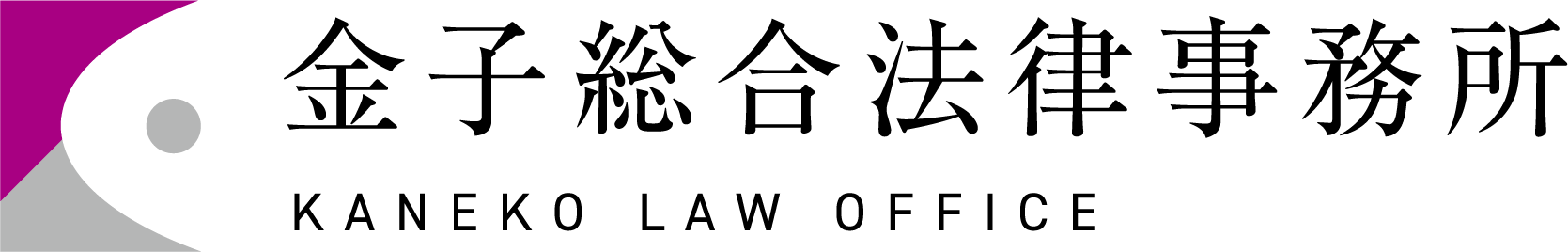本判決の内容(抜粋)
- 最高裁昭和57年3月4日第一小法廷判決
- 民法一〇三一条所定の遺留分減殺請求権は形成権であって、その行使により贈与又は遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者又は受遺者が取得した権利は右の限度で当然に遺留分権利者に帰属するものと解すべきものであることは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和四〇年(オ)第一〇八四号同四一年七月一四日第一小法廷判決・民集二〇巻六号一一八三頁、最高裁昭和五〇年(オ)第九二〇号同五一年八月三〇日第二小法廷判決・民集三〇巻七号七六八頁)、したがって、遺留分減殺請求に関する消滅時効について特別の定めをした同法一〇四二条にいう「減殺の請求権」は、右の形成権である減殺請求権そのものを指し、右権利行使の効果として生じた法律関係に基づく目的物の返還請求権等をもこれに含ましめて同条所定の特別の消滅時効に服せしめることとしたものではない、と解するのが相当である。
前提知識と簡単な解説
遺贈及び贈与の減殺請求
遺留分とは、一定の相続人のために留保されなければならない遺産の一定割合をいいます。
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び1030条に規定する贈与の減殺を請求することができます(民法1031条)。
遺留分減殺請求権は形成権であって、その権利の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によってなせば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、その意思表示がなされれば法律上当然に減殺の効力を生ずるものと解されています(最高裁昭和41年7月14日第一小法廷判決)。
また、遺留分権利者の減殺請求によって、贈与又は遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者又は受遺者が取得した権利は右の限度で当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属するものと解されています(最高裁昭和51年8月30日第二小法廷判決)。
減殺請求権の消滅時効
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないときは、時効によって消滅し、相続の開始の時から10年を経過したときも、同様に消滅します(民法1042条)。
なお、減殺の意思表示がされると、右意思表示により確定的に減殺の効力を生じることから、もはや右減殺請求権そのものについて民法1042条による消滅時効を考える余地はないとかいされています(上記最高裁昭和41年7月14日第一小法廷判決)。
本判決の意義
本件では、減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権が、民法1042条による消滅時効に服するかどうかが問題となりました。
この点について、本判決は、「遺留分減殺請求に関する消滅時効について特別の定めをした同法一〇四二条にいう「減殺の請求権」は、右の形成権である減殺請求権そのものを指し、右権利行使の効果として生じた法律関係に基づく目的物の返還請求権等をもこれに含ましめて同条所定の特別の消滅時効に服せしめることとしたものではない」と判示しました。
追記:平成30年民法改正について
平成30年民法(相続関係)改正により、遺留分権利者の権利行使によって金銭債権が生ずるものとされました(民法1046条1項)。
改正法の下では、形成権としての遺留分侵害額請求権は遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったとき時から1年間行使しないときは、時効によって消滅し(民法1048条前段)、相続開始の時から10年を経過したときも、同様に消滅するものとされています(民法1048条後段)。そして、遺留分侵害額請求権の行使によって生じた金銭債権については、通常の金銭債権と同様に、民法166条1項の規律に従って、消滅時効にかかることになります(堂薗幹一郎・野口宣大『一問一答新しい相続法』)。