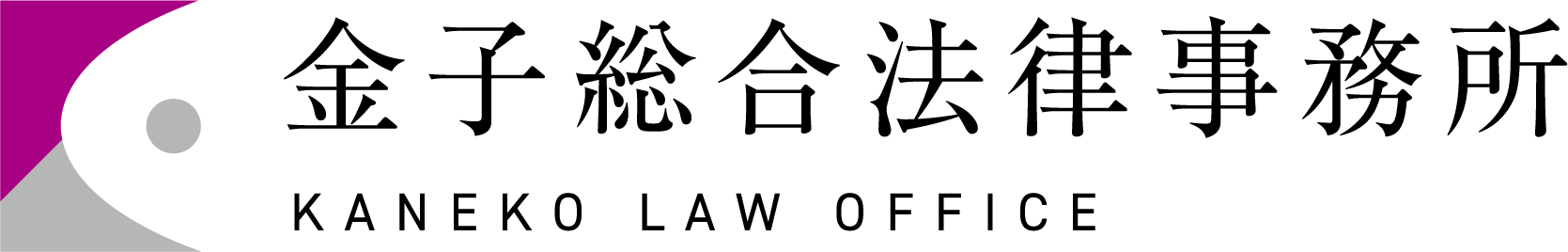本判決の内容(抜粋)
- 最高裁平成30年12月14日第二小法廷判決
1 本件は,Aに対して約37億6000万円の損害賠償債権を有する被上告人が,詐害行為取消権に基づき,上告人Y1に対しては,Aが上告人Y1から株式を代金1億6250万円で購入する旨の契約の取消し並びに受領済みの上記代金相当額及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求め,上告人Y2に対しては,Aが上告人Y2に1億2000万円を贈与する旨の契約の取消し並びに受領済みの上記贈与金相当額及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求めるなどしている事案である。
2 所論は,詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務(以下「受領金支払債務」という。)は,詐害行為の取消しを命ずる判決(以下「詐害行為取消判決」という。)の確定により生ずるから,その確定前に履行遅滞に陥ることはないのに,上告人らの被上告人に対する各受領金支払債務につき各訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を命じた原審の判断には,法令の解釈適用の誤りがある旨をいうものである。
3 そこで検討すると,詐害行為取消しの効果は詐害行為取消判決の確定により生ずるものであるが(最高裁昭和34年(オ)第99号同40年3月26日第二小法廷判決・民集19巻2号508頁参照),その効果が将来に向かってのみ生ずるのか,それとも過去に遡って生ずるのかは,詐害行為取消制度の趣旨や,いずれに解するかにより生ずる影響等を考慮して判断されるべきものである。詐害行為取消権は,詐害行為を取り消した上,逸出した財産を回復して債務者の一般財産を保全することを目的とするものであり,受益者又は転得者が詐害行為によって債務者の財産を逸出させた責任を原因として,その財産の回復義務を生じさせるものである(最高裁昭和32年(オ)第362号同35年4月26日第三小法廷判決・民集14巻6号1046頁,最高裁昭和45年(オ)第498号同46年11月19日第二小法廷判決・民集25巻8号1321頁等参照)。そうすると,詐害行為取消しの効果は過去に遡って生ずるものと解するのが上記の趣旨に沿うものといえる。また,詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領金支払債務が,詐害行為取消判決の確定より前に遡って生じないとすれば,受益者は,受領済みの金員に係るそれまでの運用利益の全部を得ることができることとなり,相当ではない。したがって,上記受領金支払債務は,詐害行為取消判決の確定により受領時に遡って生ずるものと解すべきである。そして,上記受領金支払債務は期限の定めのない債務であるところ,これが発生と同時に遅滞に陥ると解すべき理由はなく,また,詐害行為取消判決の確定より前にされたその履行の請求も民法412条3項の「履行の請求」に当たるということができる。
以上によれば,上記受領金支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥るものと解するのが相当である。
これを本件についてみると,被上告人は,上告人らに対し,訴状をもって,各詐害行為の取消しとともに,各受領済みの金員相当額の支払を請求したのであるから,上告人らの被上告人に対する各受領金支払債務についての遅延損害金の起算日は,各訴状送達の日の翌日ということになる。
前提知識と簡単な解説
詐害行為取消権
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができます(平成29年改正前民法424条1項ただし書。以下、民法の規定については、特に記載のない限り、平成29年改正前のものを指します。)。この債権者の権利を「詐害行為取消権」といいます。詐害行為取消権は、債務者の責任財産を保全するために、一般財産を減少させる債務者の行為の効力を否認して、債務者の一般財産から逸出したものを取り戻すことを目的とします。詐害行為取消権の行使の方法
詐害行為取消権は、訴えの方法により行使される必要があります(最高裁昭和39年6月12日第二小法廷判決)。そして、詐害行為取消しの効果は、取消しを命ずる判決の確定により生じます(最高裁昭和40年3月26日第二小法廷判決)。取戻しの目的物が金員の場合には、取消債権者は、受益者又は転得者に対して、自己に直接支払又は引渡しをするよう請求することができるものとされています(大審院大正10年6月18日判決)。
金製債務の遅滞の責任
金銭債務の不履行による損害賠償金を「遅延損害金」といいます。遅延損害金の額は、法定利率によります(民法419条1項本文)。ただし、法定利率を超える約定利率が定められているときは、約定利率によることとなります(民法419条1項ただし書)。
債権者が遅延損害金を請求するには損害の証明をすることを要せず、債務者は不可抗力をもって支払を拒むことはできません(民法419条2項)。
遅延損害金が発生するのは、履行遅滞となった時からです。履行遅滞となる時期は、(a) 確定期限のある債務については、その期限の到来した時(民法412条1項)、(b) 不確定期限のある債務については、債務者が期限の到来を知った時(民法412条2項)、(c) 期限の定めのない債務については、債務者が履行の請求を受けた時(民法412条3項)とされています。
本判決の意義
本件では、詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務について、履行遅滞となる時期が問題となりました。この点について、本判決は、「履行の請求を受けた時に遅滞に陥る」と判示しました。