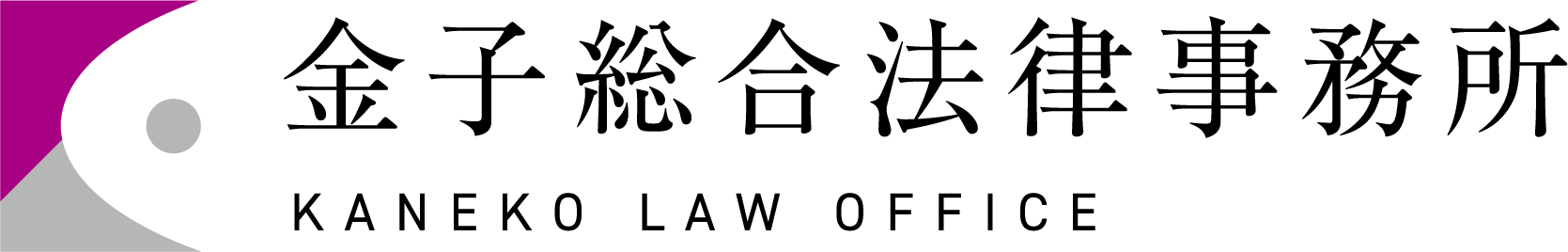- 民法第424条
- 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
- 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
- 債権者は、その債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
- 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
- 平成29年改正前民法第424条
- 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
- 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
条文の趣旨と解説
詐害行為取消権は、債務者の責任財産を保全するために、一般財産を減少させる債務者の行為の効力を否認して、債務者の一般財産から逸出したものを取り戻すことを目的とする制度です。
債務者の責任財産保全を目的とする制度であることから、詐害行為取消権を有する「債権者」(本条1項)は、金銭債権を有する者に限られます。もっとも、判例は、特定物引渡債権についても「窮極において損害賠償債権に変じうるのであるから、債務者の一般財産により担保されなければならないことは、金銭債権と同様」であり、したがって「目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には、該特定物債権者は右処分行為を詐害行為として取り消すことができる」と判示しています(最高裁昭和36年7月19日大法廷判決)。
詐害行為取消の対象とならない行為
財産権を目的としない行為は、詐害行為取消の対象とはなりません(本条2項)。したがって、婚姻や縁組、相続の承認又は放棄のような身分行為については、詐害行為取消の対象とはなりません(相続の放棄につき、最高裁昭和49年9月20日第二小法廷判決。)。身分行為については、他人の意思によってこれを強制すべきでないと考えられるからです。
もっとも、離婚に伴う財産分与は、身分行為と直接に関係のない財産処分行為であるようにも思われることから、詐害行為取消の対象となるかどうかが問題となります。
判例は、「分与者が既に債務超過の状態にあって当該財産分与によって一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になるとしても、それが民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為として、債権者による取消の対象となりえないものと解する」と判示しました(最高裁昭和58年12月19日第二小法廷判決)。なお、「特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消される」ことになります(最高裁平成12年3月9日第一小法廷判決)。
共同相続人の間で成立した遺産分割協議(907条1項)が詐害行為取消権行使の対象となるかどうかについては、判例は、「遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができる」として、「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解する」と判示しました(最高裁平成11年6月11日第二小法廷判決)。
平成29年民法(債権関係)改正
本条第1項本文
改正前民法第424条第1項本文の規律の内容を基本的に維持していますが、取消の対象が「法律行為」から「行為」に改められました。これは、改正前民法下においても、詐害行為の対象は、法律行為に限らず、弁済や時効更新事由としての債務の承認(152条1項)、法定追認の効果を生ずる行為(125条)などを含むと解されていたことを理由とします(『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』)。本条第1項ただし書
改正前民法第424条第1項ただし書は、受益者に加えて、転得者に関する規律も定めていましたが、改正民法では、転得者に対する詐害行為取消権の要件については規律を分け、改正民法424条の5において定められることとなりました。本条第3項
改正前民法は、被保全債権の要件について特段の規律を定めていませんでした。改正前民法下における判例は、被保全債権の成立時期に関し、被保全債権は詐害行為の前に発生したものであることを要するとしながらも(大審院大正6年1月22日判決)、例外的に、将来の婚姻費用の支払に関する債権(最高裁昭和46年9月21日第三小法廷判決)など、厳密には被保全債権が詐害行為の前に発生していないとも考えられる事案においても、詐害行為取消権の行使を認めていました。
このような判例を踏まえ、改正民法は、破産法第2条第5項の定義を参考としつつ、被保全債権の要件について、詐害行為の「前の原因に基づいて生じたもの」であることを要すると定めています(部会資料73A)。
本条第4項
改正前民法下においては明文はなかったものの、詐害行為取消権が責任財産を保全して強制執行の準備をするための制度であることから、強制執行により実現することができない債権を被保全債権として詐害行為取消権を行使することは認められないものと解されていました。そこで、改正民法では、このような解釈が明文化されました。
詐害行為取消権の行使方法
詐害行為取消権は「裁判所に請求」して行使します(本条1項)。判例は、「詐害行為の取消は訴の方法によるべきものであつて、抗弁の方法によることは許されないものと解する」と判示しています(最高裁昭和39年6月12日第二小法廷判決)。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 債権の効力
- 詐害行為取消権
- 民法第424条 – 詐害行為取消請求
- 民法第424条の2 – 相当の対価を得てした財産の処分行為の特則
- 民法第424条の3 – 特定の債権者に対する担保の供与等の特則
- 民法第424条の4 – 過大な代物弁済等の特則
- 民法第424条の5 – 転得者に対する詐害行為取消請求
- 民法第424条の6 – 財産の返還又は価額の償還の請求
- 民法第424条の7 – 被告及び訴訟告知
- 民法第424条の8 – 詐害行為の取消しの範囲
- 民法第424条の9 – 債権者への支払又は引渡し
- 民法第425条 – 認容判決の効力が及ぶ者の範囲
- 民法第425条の2 – 債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利
- 民法第425条の3 – 受益者の債権の回復
- 民法第425条の4 – 詐害行為取消請求を受けた転得者の権利
- 民法第426条 – 詐害行為取消権の期間の制限
- 詐害行為取消権
- 債権の効力
- 総則
- 債権