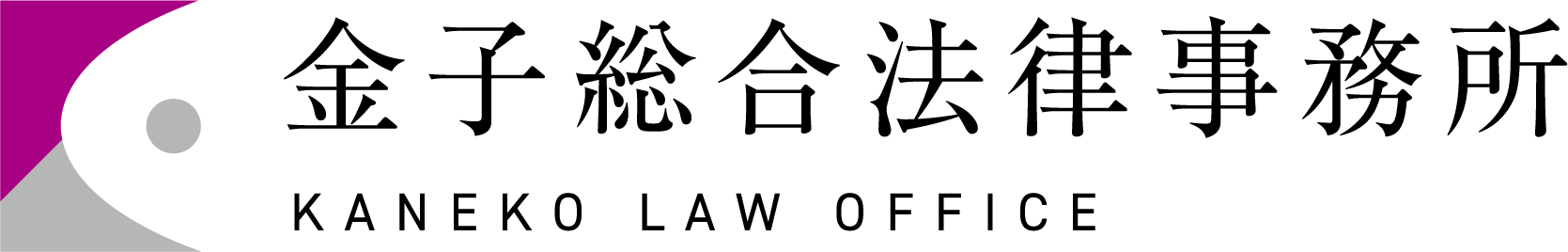- 民法第424条の3
-
債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
- その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。
- その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
- 前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
- その行為が、債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること。
- その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
-
債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
条文の趣旨と解説
平成29年民法改正により、新設された規定です。
改正前民法では、詐害行為につき「債権者を害することを知ってした法律行為」(改正前民法424条1項)という概括的な規定のみが置かれていました。
一方で、破産法は、平成16年倒産法改正に際し、否認の対象となる行為について、類型ごとに要件・効果の見直しが行われました。否認の対象は明確にし限定されたとしても、詐害行為取消しの対象がなお不明確かつ広範であると、経済的危機に直面した債務者と取引をする相手方が萎縮してしまうという問題等が指摘されていました。
特定の債権者に対する担保の供与又は債務消滅行為について
改正前民法下における判例法理
債務消滅行為に関して、改正前民法下における判例は、「弁済は、原則として詐害行為とならず、唯、債務者が一債権者と通謀し、他の債権者を害する意思をもつて弁済したような場合にのみ詐害行為となる」としていました(最高裁昭和33年9月26日第二小法廷判決)。また、既存債務に対する担保の供与に関しては、「債務者が或債権者のために根抵当権を設定するときは、当該債権者は、担保の目的物につき他の債権者に優先して、被担保債権の弁済を受け得られることになるので、それだけ他の債権者の共同担保は減少する」から詐害行為に当たりうるが(最高裁昭和32年11月1日第二小法廷判決)、事業の継続のため合理的な範囲を超えない範囲で行った場合などには、詐害行為とならないとの立場を採っていました(最高裁昭和44年12月19日第一小法廷判決参照)。
破産法の規定
破産法は、既存の債務についてされた担保供与や債務の消滅に関する行為については、「破産者が支払不能になった後若しくは破産手続開始の申立てがあった後」に行われたものについてのみ、否認の対象としています(破産法162項1項1号)。その上で、代物弁済や期限前弁済など「破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為」については、支払不能になる前30日以内にされたものにまで、否認の対象を拡張しています(破産法161条1項2号)。
改正民法の内容
本条は、破産法の趣旨を導入しつつ、判例法理を明文化するという観点から、既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為に関する詐害行為取消権の要件を定めます。すなわち、当該行為が、(1)債務者が支払不能の時に行われたものであること、(2)債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであることを満たせば、詐害行為取消権を行使することができます(本条1項)。
また、上記要件を満たさない場合であっても、当該行為が、(a)債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものであること、(b)債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること、(c)債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであることを満たせば、詐害行為取消権を行使することができます(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 債権の効力
- 詐害行為取消権
- 民法第424条 – 詐害行為取消請求
- 民法第424条の2 – 相当の対価を得てした財産の処分行為の特則
- 民法第424条の3 – 特定の債権者に対する担保の供与等の特則
- 民法第424条の4 – 過大な代物弁済等の特則
- 民法第424条の5 – 転得者に対する詐害行為取消請求
- 民法第424条の6 – 財産の返還又は価額の償還の請求
- 民法第424条の7 – 被告及び訴訟告知
- 民法第424条の8 – 詐害行為の取消しの範囲
- 民法第424条の9 – 債権者への支払又は引渡し
- 民法第425条 – 認容判決の効力が及ぶ者の範囲
- 民法第425条の2 – 債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利
- 民法第425条の3 – 受益者の債権の回復
- 民法第425条の4 – 詐害行為取消請求を受けた転得者の権利
- 民法第426条 – 詐害行為取消権の期間の制限
- 詐害行為取消権
- 債権の効力
- 総則
- 債権