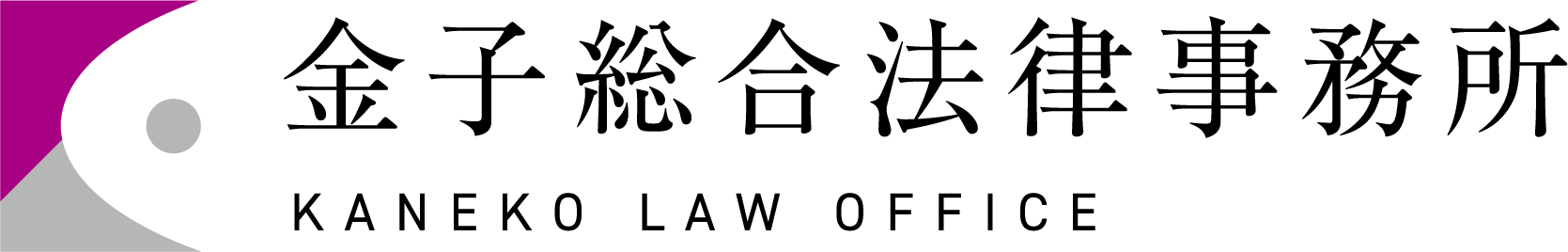主な取扱業務
ご依頼までの流れ
業務方針
親身にお話を伺います
依頼者の真の利益を実現しようとするとき、法律だけに目を向けていればいいというわけではないと考えています。
依頼者の胸中、過去のいきさつ、取り巻く事情を十分に汲み取ることができるよう、幅広く、そして深く、依頼者のお話を伺います。
適宜に進捗状況を報告します
トラブルという不安を抱えているときには、たった一歩の前進が分かるだけでも、安堵の胸をなで下ろすことができるものです。
このような観点から、お任せ頂いた案件の進み具合を適宜にお知らせすることも、弁護士のサービスの一環であると考えております。
適正な解決を心掛けます
弁護士に資格が必要とされているのは、弁護士としての活動が、社会正義の実現という公益的な役割も担っているからだと考えます。
社会正義が歪められている状況を正すことが、弁護士に与えられた使命であることを心に銘し、ひとつひとつのご依頼に取り組んで参ります。
弁護士のプロフィール

- 弁護士 金子 剛
- 金子総合法律事務所・栃木県弁護士会所属
経歴
- 2001.3
- 栃木県立真岡高校卒業
- 2005.3
- 東北大学法学部卒業
- 2005.11
- 司法試験合格
- 2007.9
- 司法修習後、東京都内の法律事務所勤務
- 2019.11
- 栃木県真岡市にて法律事務所開業