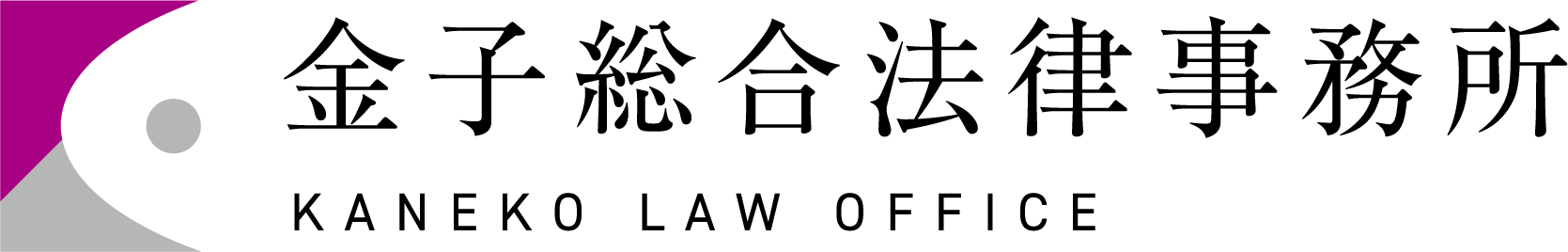- 民法第258条
- 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
- 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
- 共有物の現物を分割する方法
- 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
- 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
- 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
- 令和3年改正前民法第258条
- 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
- 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
条文の趣旨と解説
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき等は、裁判所に分割を請求することができます。
令和3年民法・不動産登記法改正について
共有者間の協議
改正前民法では、共有物分割請求訴訟を提起するためには「共有者間に協議が調わない」ことを要すると定められていました。もっとも、改正前民法下における解釈により、「協議が調わないとき」には、はじめから協議をすることができない場合、すなわち、一部の共有者が協議に応じない場合等も含むものと解されていました。そこで、改正民法は、この解釈を明文化し、「協議をすることができないとき」にも裁判所に分割を請求することができると規定されています(本条1項)。
分割の方法
改正前民法は、裁判所が共有物を分割する方法として、共有物の現物を分割する「現物分割」と、分割によって価格を著しく減少させるおそれがある場合に競売を命じる「競売分割」の2種類のみを定めていました。しかし、改正前民法下における判例は、裁判所による共有物の分割の本質が非訟事件であるとの理解に立ち、「当該共有物の性質及び形状、共有関係の発生原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情を総合的に考慮し、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が存するときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法、すなわち全面的価格賠償の方法による分割をすることも許される」と判示していました(最高裁平成8年10月31日第一小法廷判決)。
そこで、改正民法では、共有物分割方法の多様化・弾力化を図る判例法理を維持し、共有物分割の方法として、(1) 現物分割(本条2項1号)、(2) 価格賠償(本条2項2号)、(3) 競売分割(本条3項)を規定しています。
金銭債務の履行を確保するための手続的措置
価格賠償の方法による場合に現物取得者の金銭債務の履行を確保するため、改正民法は、裁判所が、金銭の支払い、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができるものと定めています(本条4項)。条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 所有権
- 共有
- 民法第249条 - 共有物の使用
- 民法第250条 – 共有持分の割合の推定
- 民法第251条 – 共有物の変更
- 民法第252条 – 共有物の管理
- 民法第252条の2 – 共有物の管理者
- 民法第253条 – 共有物に関する負担
- 民法第254条 – 共有物についての債権
- 民法第255条 – 持分の放棄及び共有者の死亡
- 民法第256条 – 共有物の分割請求
- 民法第257条 – 共有物の分割請求
- 民法第258条 – 裁判による共有物の分割
- 民法第258条の2 – 裁判による共有物の分割
- 民法第259条 – 共有に関する債権の弁済
- 民法第260条 – 共有物の分割への参加
- 民法第261条 – 分割における共有者の担保責任
- 民法第262条 – 共有物に関する証書
- 民法第262条の2 – 所在等不明共有者の持分の取得
- 民法第262条の3 – 所在等不明共有者の持分の譲渡
- 民法第263条 – 共有の性質を有する入会権
- 民法第264条 – 準共有
- 共有
- 所有権
- 物権