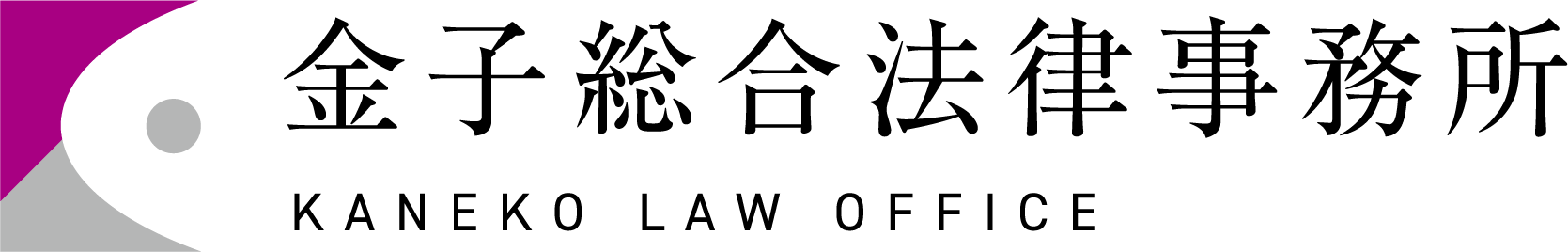- 民法第436条
- 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
- 平成29年改正前民法第432条
- 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
条文の趣旨と解説
債務の目的がその性質上可分な場合に、数人の債務者が独立に全部の給付をなすべき債務を負担し、そのうちの一人の給付があれば他の債務者も債務を免れる多数当事者の債務を「連帯債務」といいます。
平成29年民法(債権関係)改正 – 連帯債務の成立要件
改正前民法においては「数人が連帯債務を負担するときは」との文言があるのみで、連帯債務の成立要件について明確に定められていませんでした。
改正民法では、まず性質上可分であるか不可分であるかという基準を導入し、債務の内容が性質上可分である場合には、原則として分割債務となるが(427条)、法令の規定又は当事者の意思表示があるときは、連帯債務を負担するものとしています(本条)。債務の内容が性質上不可分である場合には、各債務者は不可分債務を負担します(430条)。
法令の規定により連帯債務とされる例
- 併存的債務引受
→ 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担します(470条1項)。 - 共同不法行為
→ 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負います(719条1項)。 - 日常の家事に関する債務
→ 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負います(761条本文)。 - 商行為となる行為によって債務を負担したとき
→ 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担します(商法511条1項)。
債権者と債務者との間の効力
債権者は、連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に、全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができます。
連帯債務者の全員又はそのうちの数人若しくは一人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてそれぞれの破産手続に参加することができます(破産法104条1項)。再生手続開始の決定があったとき、更生手続開始の決定があったときも、同様です(民事再生法86条2項、会社更生法135条2項)