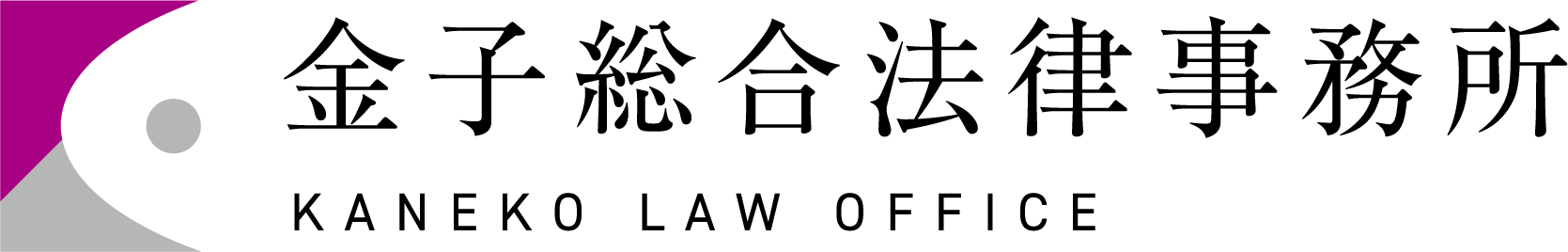- 民法第441条
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
- 平成29年改正前民法第440条
- 第434条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
- 平成29年改正前民法第434条(改正により削除)
- 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。
- 平成29年改正前民法第437条(改正により削除)
- 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。
- 平成29年改正前民法第439条(改正により削除)
- 連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、その義務を免れる。
条文の趣旨と解説
連帯債務者の一人について生じた事由については、他の債務者に影響を及ぼさないことを原則としつつ(相対的効力の原則)、当事者間の法律関係の簡易な決済及び公平の見地から、一定の事由(更改、相殺及び混同)については、全ての債務者のために効力を生ずるものとされています(絶対的効力事由)。
相対的効力の例としては、時効の完成(166条)、時効の完成猶予及び更新(147条以下)、付遅滞の要件としての履行の請求(412条2項、3項)、債務の免除(519条)などがあります。
なお、明文の規定はないものの、連帯債務は客観的に単一の目的を有するものであることから、弁済(473条)、代物弁済(482条)又は供託(494条)など、連帯債務の目的を達成させる事由は、絶対的効力を有するものとされています。
平成29年民法(債権関係)改正
改正前民法においては、絶対的効力事由として以下の事由を定めていました。- 履行の請求(改正前民法434条)
- 更改(改正前民法435条)
- 相殺(改正前民法436条)
- 免除(改正前民法437条)
- 混同(改正前民法438条)
- 時効の完成(改正前民法439条)
履行の請求
改正前民法434条は、連帯債務者の一人に対する履行の請求を絶対的効力事由として定めていましたが、履行の請求を受けていない連帯債務者が、自分の知らない間に履行遅滞に陥ったり、消滅時効が中断したりするのは、連帯債務者間に緊密な関係が存在しない場合には、他の債務者にとって不意打ちになりかねず、債務者にとって不利益が大きいとの批判がありました。一方で、ペアローンなど、履行の請求が絶対的効力を有することについて実務上の有用性が認められ、かつ不当ではない場面もあり得るとの議論もありました。そこで、改正民法は、履行の請求について、改正前民法434条を削除し、相対的効力事由とすることを原則としつつ、債権者と他の債務者との間に別段の合意がある場合には、絶対的効力が生じるものとしています(本条ただし書)。
免除
改正前民法437条は、連帯債務者の一人に対する免除したときは、その債務者の負担部分について、他の債務者も債務を免れる旨を定めていました。この規定は、当事者間の法律関係を簡易に決済しようとする趣旨であると解されていました。しかし、債権者において連帯債務者の一人の債務を免除することは、単にその連帯債務者には自分からは請求をしないという意思を有しているに過ぎず、他の連帯債務者に対してまでは債務の免除をするという意思を有していないことも考えられます。その場合には債権者の意思に反するという批判がありました。
そこで、改正民法は、連帯債務者の一人に対する免除は、改正前民法437条を削除し、相対的効力事由とすることを原則としつつ、当事者間の別段の合意によって絶対的効力事由を生じさせることは妨げないこととしています(本条ただし書)。
時効の完成
改正前民法439条は、連帯債務者の一人のために消滅時効が完成したときは、その債務者の負担部分については、他の債務者もまたその義務を免れる旨を定めていました。しかし、資力ある債務者の時効を中断しておいても、他の者の時効を中断措置を講じておかなければ全額についての時効中断とはならず、時効管理面でのリスクを債権者に負わせているという批判がありました。
そこで、改正民法は、連帯債務者の一人についての時効の完成には相対的効力しか認められないことを原則としつつ、別段の合意があるときは、当該連帯債務者については、絶対的効力が及ぶこととしました(本条ただし書)。