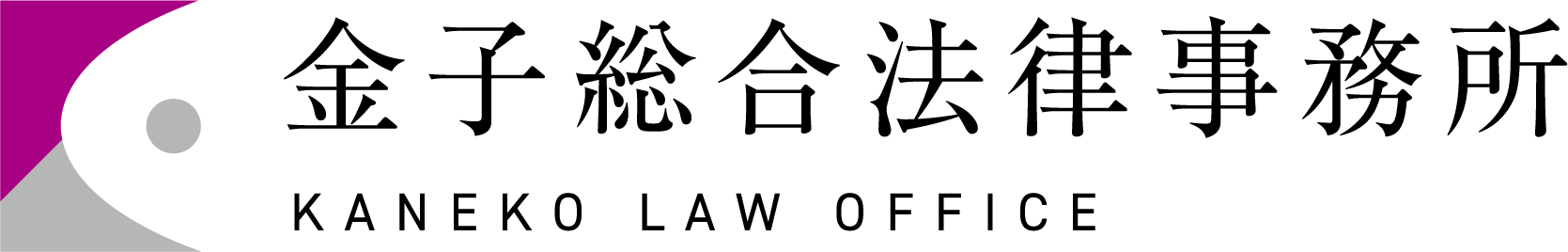- 民法第486条
- 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
- 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
- 令和3年改正前民法第486条
- 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
- 平成29年改正前民法第486条
- 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
条文の趣旨と解説
二重弁済の危険を防止するとともに、後日紛争となった場合に弁済の事実を証明する手段として、民法は、弁済者のために、受取証書の交付を請求する権利を認めました(本条1項)。
平成29年改正
平成29年改正前民法においては、明文の規定は存しなかったものの、弁済の証拠としての重要性から、弁済と受取証書の交付とは同時履行の関係に立つと解されていました。
そこで、平成29年民法(債権関係)改正では、当該解釈に基づき、規定が改められました。
令和3年改正
本条2項は、令和3年5月12日成立の「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)により新設された規定です(施行日は令和3年9月1日)。
改正の趣旨は、弁済者側において電磁的記録の提供を受けたいというニーズがあることや、弁済受領者側において受取証書の交付が過度な負担となる場面があること、今後ますます取引実務のデジタル化が進むと考えられることに鑑み、受取証書の交付の請求に代えて電磁的記録の提供の請求を行うことができるよう措置を講ずることとしたものです。
電子的な受取証書の記載内容や提供の方法等については、内閣府・法務省『電子的な受取証書(新設された民法第 486 条第2項関係)についてのQ&A』に、参考となる解釈が記載されています。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 債権の消滅
- 弁済
- 総則
- 民法第473条 - 弁済
- 民法第474条 – 第三者の弁済
- 民法第475条 – 弁済として引き渡した物の取戻し
- 民法第476条 – 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力
- 民法第477条 – 預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済
- 民法第478条 – 受領権者としての外観を有する者に対する弁済
- 民法第479条 – 受領権者以外の者に対する弁済
- 民法第481条 – 差押えを受けた債権の第三債務者の弁済
- 民法第482条 – 代物弁済
- 民法第483条 – 特定物の現状による引渡し
- 民法第484条 – 弁済の場所及び時間
- 民法第485条 – 弁済の費用
- 民法第486条 – 受取証書の交付請求
- 民法第487条 – 債権証書の返還請求
- 民法第488条 – 同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当
- 民法第489条 – 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当
- 民法第490条 – 合意による弁済の充当
- 民法第491条 – 数個の給付をすべき場合の充当
- 民法第492条 – 弁済の提供の効果
- 民法第493条 – 弁済の提供の方法
- 総則
- 弁済
- 債権の消滅
- 総則
- 債権