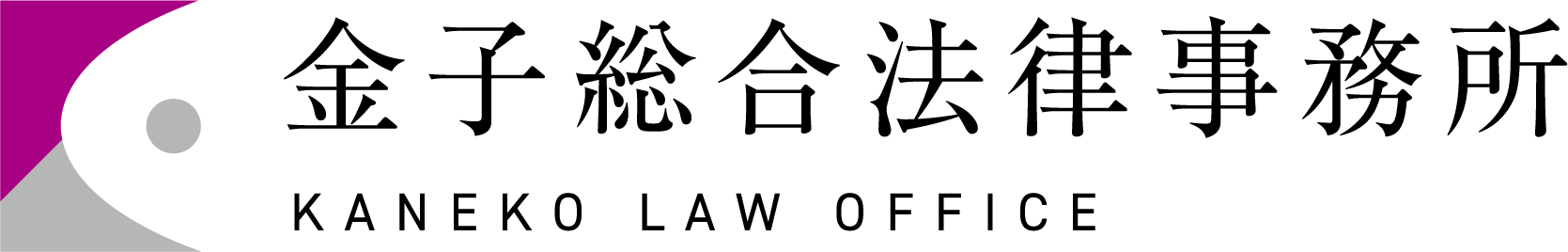- 民法第465条
- 第442条から第444条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
- 第462条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
条文の趣旨と解説
同一の主たる債務について数人が保証債務を負担することを共同保証といいますが、本条は、共同保証人間の求償関係を定めています。
共同保証について
共同保証人間の求償関係を説明する前提として、共同保証が行われた場合の法律関係について概観します。債権者との関係では、それぞれ保証人が各別の契約で保証したときであっても、別段の意思表示がないときは、原則として共同保証人は、主たる債務の額を平等の割合で分割した額について、保証債務を負担します(456条において準用する427条)。これは「分別の利益」と呼ばれています。
分別の利益を有しない例外として、(1) 主たる債務が不可分である場合、(2) 各保証人が全額を弁済すべき旨の特約がある場合(保証連帯)、(3) 連帯保証の場合、があります。
共同保証人間の一人が、弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為をしたとき、主たる債務者に対して求償権を行使することができます(459条、459条の2、462条)。
さらに、他の共同保証人に対しても、求償権を行使することができます(本条)。
共同保証人間の求償関係
共同保証人相互間においては、分別の利益の有無に応じて、求償できる範囲が異なります。分別の利益を有しない場合
一人の保証人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときは、連帯債務者相互間の関係と同一に取り扱われます(本条1項)。すなわち、連帯債務者間の求償権(442条)、通知を怠った連帯債務者の求償の制限(443条)、償還をする資力のない者の負担部分の分担(444条)の規定が準用されます。分別の利益を有する場合
共同保証人が分別の利益を有する場合は、債権者に対して自己の負担部分を超えて弁済すべき義務はないため、委託を受けない保証人と類似します。そこで、共同保証人が分別の利益を有する場合において、一人の保証人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときは、委託を受けない保証人の求償権の規定である462条が準用されます(本条2項)。条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 多数当事者の債権及び債務
- 保証債務
- 総則
- 民法第446条 - 保証人の責任等
- 民法第447条 – 保証債務の範囲
- 民法第448条 – 保証人の負担と主たる債務の目的又は態様
- 民法第449条 – 取り消すことができる債務の保証
- 民法第450条 – 保証人の要件
- 民法第451条 – 他の担保の供与
- 民法第452条 – 催告の抗弁
- 民法第453条 – 検索の抗弁
- 民法第454条 – 連帯保証の場合の特則
- 民法第455条 – 催告の抗弁及び検索の抗弁の効果
- 民法第456条 – 数人の保証人がある場合
- 民法第457条 – 主たる債務者について生じた事由の効力
- 民法第458条 – 連帯保証人について生じた事由の効力
- 民法第458条の2 – 主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務
- 民法第458条の3 – 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務
- 民法第459条 – 委託を受けた保証人の求償権
- 民法第459条の2 – 委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権
- 民法第460条 – 委託を受けた保証人の事前の求償権
- 民法第461条 – 主たる債務者が保証人に対して償還をする場合
- 民法第462条 – 委託を受けない保証人の求償権
- 民法第463条 – 通知を怠った保証人の求償の制限等
- 民法第464条 – 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権
- 民法第465条 – 共同保証人間の求償権
- 総則
- 保証債務
- 多数当事者の債権及び債務
- 総則
- 債権