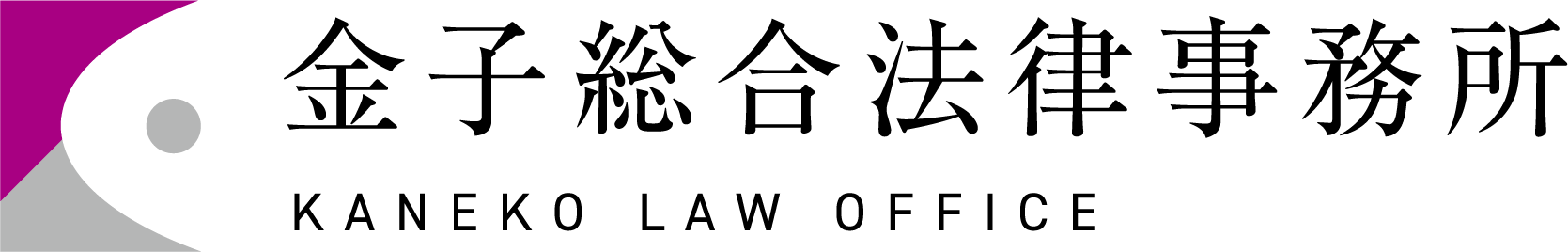- 金子総合法律事務所
- 企業経営の法律知識
- 暮らしの法律知識
- フリーランスが仕事を請ける際に確認すべき契約書の項目
- 不動産登記の調べ方
- 労働審判手続について
- ケーキの分け方と遺産の分割
- 戸籍の調べ方 ~ 戸籍謄本の取り寄せ方
- 離婚の流れと夫婦間で決めておくこと
- 少額訴訟の流れ - 債権回収のひとつの手段
- 商業登記の調べ方 〜 登記事項証明書について
- 法律専門家の探し方
- 法関連リンク集
- 不動産の基礎知識
- 債務整理の基礎知識
- 相続の基礎知識
- 遺産の範囲 - 相続の対象
- 相続放棄の手続の流れと必要書類
- 遺産分割調停を利用する - 申立ての方法と調停の流れ
- 遺産の取り分 – 法定相続分と特別受益・寄与分
- 自筆証書遺言の書き方
- 相続した不動産を分ける3つの方法について
- 遺言書の作り方 – 遺言の方式
- 遺言書の検認と開封
- 遺言でできること - 有効な遺言をするために
- 遺産の分け方 - 遺産分割
- 内縁の妻は遺産を相続できますか?
- 遺産は誰が相続する? - 法定相続人の範囲について
- 遺言書を開封する手続があることを知っていますか?
- 資産がなければ相続は関係ない?相続放棄という選択肢
- 相続財産に関する費用は誰が負担する?
- 相続がはじまる - 相続の開始と失踪宣告
- 生命保険の死亡保険金は相続財産になりますか?
- 代襲相続 - 相続するはずだった人が既に亡くなっている場合
- 相続開始前に遺留分を放棄してもらうことはできますか?
- 法改正の概要
- 重要な判例・裁判例の紹介
- 相続の開始後に認知された者が価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時と支払債務が履行遅滞に陥る時期(最高裁平成28年2月26日第二小法廷判決)
- 財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合における債務の承継と遺留分の侵害額の算定(平成21年3月24日最高裁第三小法廷判決)
- 遺言書に花押を書いても押印とは認められない(最高裁平成28年6月3日第二小法廷判決)
- 「相続させる」遺言により相続するものとされた推定相続人が、遺言者よりも先に死亡した場合における代襲相続の可否(平成23年2月22日最高裁第三小法廷判決)
- 妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置(最高裁平成26年10月23日第一小法廷判決)
- 信託契約の解約により再生債権者が負担した解約金支払債務と相殺(最高裁平成26年6月5日第一小法廷判決)
- 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者の、再審の訴えにおける原告適格(最高裁平成25年11月21日第一小法廷判決)
- 非免責債権に該当することを理由として提起した執行文付与の訴え(最高裁平成26年4月24日第一小法廷判決)
- 成年後見開始の審判と遺留分減殺請求権の消滅時効(最高裁平成26年3月14日第二小法廷判決)
- 不動産の登記に関する訴訟における権利能力のない社団の原告適格(最高裁平成26年2月27日第一小法廷判決)
- 再生債権として届出がされた共益債権の行使(最高裁平成25年11月21日第一小法廷判決)
- 商法266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率(最高裁平成26年1月30日第一小法廷判決)
- 共同相続された投資信託受益権と個人向け国債(最高裁平成26年2月25日第三小法廷判決)
- 自己の相続分の全部を譲渡した者の遺産確認の訴えにおける当事者適格(最高裁平成26年2月14日第二小法廷判決)
- 共有物について遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合(最高裁平成25年11月29日第二小法廷判決)
- 保証人が主たる債務を相続したことを知りながらした保証債務の弁済と時効中断の効力(最高裁平成25年9月13日第二小法廷判決)
- 民法900条4号ただし書前段の規定の憲法14条1項適合性(最高裁平成25年9月4日大法廷決定)
- 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権の相殺適状(最高裁平成25年2月28日第一小法廷判決)
- ゴルフ場経営を目的とする地上権設定契約及び土地賃貸借契約と借地借家法の地代等増減額請求(最高裁平成25年1月22日第三小法廷判決)
- 根保証契約の被保証債権が元本期日前に譲渡された場合における保証債務の履行請求(最高裁平成24年12月14日第二小法廷判決)
- 新設分割と詐害行為取消権(最高裁平成24年10月12日第二小法廷判決)
- 債務整理開始通知をした行為の破産法162条1項1号イ及び3項「支払の停止」への該当性(最高裁平成24年10月19日第二小法廷判決)
- 不法原因給付と破産管財人の不当利得返還請求(東京高裁平成24年5月31日判決)
- 保証人が取得する求償債権の破産債権該当性および相殺の可否(最高裁平成24年5月28日第二小法廷判決)
- 賃料債権の差押えと目的物の賃借人への譲渡による賃貸借契約の終了(最高裁平成24年9月4日第三小法廷判決)
- 共済契約と破産管財人による共済金請求(札幌地裁平成24年3月29日判決)
- 抵当権設定登記と再度の取得時効(最高裁平成24年3月16日第二小法廷判決)
- 安全配慮義務違反と弁護士費用(最高裁平成24年2月24日第二小法廷判決)
- 相続分の指定と遺留分減殺請求(最高裁平成24年1月26日第一小法廷決定)
- 預金者の共同相続人の一人は、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(最高裁平成21年1月22日第一小法廷判決)
- 共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力(最高裁平成17年9月8日第一小法廷判決)
- 遺産分割協議と詐害行為取消権(最高裁平成11年6月11日第二小法廷判決)
- 相続に関して不当な利益を目的とするものでない遺言書の破棄又は隠匿行為と相続欠格者の該当性(最高裁平成9年1月28日第三小法廷判決)
- 共同相続人の一人が被相続人の許諾を得て遺産である建物に被相続人と同居してきたときは、同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認される(最高裁平成8年12月17日第三小法廷判決)
- 公営住宅の入居者が死亡した場合、その相続人は当該公営住宅を使用する権利を承継しない(最高裁平成2年10月18日第一小法廷判決)
- 遺言書又はその訂正が方式を欠き無効である場合に、方式を具備させて有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為と相続欠格者の該当性(最高裁昭和56年4月3日第二小法廷判決)
- 共同相続人の一人によって相続権を侵害された他の共同相続人が侵害の排除を求める場合における民法884条の適用(最高裁昭和53年12月20日大法廷判決)
- 死亡退職金の受給権は、受給権者である遺族が自己固有の権利として取得し、相続財産に属さないとされた事例(最高裁昭和55年11月27日第一小法廷判決)
- 保険金受取人の指定のないときは保険金を被保険者の相続人に支払う旨の約款の条項は、保険金受取人の指定と同視できる(最高裁昭和48年6月29日第二小法廷判決)
- 使用貸借の貸主が数名あるとき、各貸主は、使用貸借の終了に基づき、総貸主のため家屋全部の明渡を請求することができる(最高裁昭和42年8月25日第二小法廷判決)
- 共有物の持分の価格が過半数をこえる者が、共有物を単独で占有する他の共有者に対して、当然には、その共有物の明渡請求をすることはできない(最高裁昭和41年5月19日第一小法廷判決)
- 保険金受取人を「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定したときの養老保険契約における保険金請求権の帰属(最高裁昭和40年2月2日第三小法廷判決)
- 共同相続人が相続財産である不動産を目的とする賃貸借を解除するときは、過半数で決する(最高裁昭和39年2月25日第三小法廷判決)
- 継続的取引について将来負担する事のあるべき債務についてした責任の限度額及び期間の定めのない連帯保証契約における保証人たる地位の相続性(最高裁昭和37年11月9日第二小法廷判決)
- 相続財産の共有の性質(最高裁昭和30年5月31日第三小法廷判決)
- サイトマップ
- 法律相談の予約
- プロフィール
- 弁護士費用
- 取扱業務
- 弁護士事務所へのアクセス
- よくあるご質問
- 免責事項
- 法律相談の流れ
- 民法の解説
- 総則
- 人
- 民法第3条の2 – 意思能力
- 行為能力
- 民法第4条 – 成年
- 民法第5条 – 未成年者の法律行為
- 民法第6条 – 未成年者の営業の許可
- 民法第7条 – 後見開始の審判
- 民法第8条 – 成年被後見人及び成年後見人
- 民法第9条 – 成年被後見人の法律行為
- 民法第10条 – 後見開始の審判の取消し
- 民法第11条 – 保佐開始の審判
- 民法第12条 – 被保佐人及び保佐人
- 民法第13条 – 保佐人の同意を要する行為等
- 民法第14条 – 保佐開始の審判等の取消し
- 民法第15条 – 補助開始の審判
- 民法第16条 – 被補助人及び補助人
- 民法第17条 – 補助人の同意を要する旨の審判
- 民法第18条 – 補助開始の審判等の取消し
- 民法第19条 – 審判相互の関係
- 民法第20条 – 制限行為能力者の相手方の催告権
- 民法第21条 – 制限行為能力者の詐術
- 住所
- 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
- 民法第32条の2 – 同時死亡の推定
- 物
- 法律行為
- 意思表示
- 代理
- 民法第99条 – 代理行為の要件及び効果
- 民法第100条 – 本人のためにすることを示さない意思表示
- 民法第101条 – 代理行為の瑕疵
- 民法第102条 – 代理人の行為能力
- 民法第103条 – 権限の定めのない代理人の権限
- 民法第104条 – 任意代理人による復代理人の選任
- 民法第105条 – 法定代理人による復代理人の選任
- 民法第106条 – 復代理人の権限等
- 民法第107条 – 代理権の濫用
- 民法第108条 – 自己契約及び双方代理等
- 民法第109条 – 代理権授与の表示による表見代理等
- 民法第110条 – 権限外の行為の表見代理
- 民法第111条 – 代理権の消滅事由
- 民法第112条 – 代理権消滅後の表見代理等
- 民法第113条 – 無権代理
- 民法第114条 – 無権代理の相手方の催告権
- 民法第115条 – 無権代理の相手方の取消権
- 民法第116条 – 無権代理行為の追認
- 民法第117条 – 無権代理人の責任
- 民法第118条 – 単独行為の無権代理
- 無効及び取消し
- 条件及び期限
- 期間の計算
- 時効
- 総則
- 民法第144条 – 時効の効力
- 民法第145条 – 時効の援用
- 民法第146条 – 時効の利益の放棄
- 民法第147条 – 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
- 民法第148条 – 強制執行等による時効の完成猶予
- 民法第149条 – 仮差押え等による時効の完成猶予
- 民法第150条 – 催告による時効の完成猶予
- 民法第151条 – 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
- 民法第152条 – 承認による時効の更新
- 民法第153条 – 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲
- 民法第154条 – 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲
- 民法第158条 – 未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予
- 民法第159条 – 夫婦間の権利の時効の完成猶予
- 民法第160条 – 相続財産に関する時効の完成猶予
- 民法第161条 – 天災等による時効の完成猶予
- 取得時効
- 消滅時効
- 総則
- 人
- 物権
- 占有権
- 占有権の取得
- 占有権の効力
- 民法第188条 – 占有物について行使する権利の適法の推定
- 民法第189条 – 善意の占有者による果実の取得等
- 民法第190条 – 悪意の占有者による果実の返還等
- 民法第191条 – 占有者による損害賠償
- 民法第192条 – 即時取得
- 民法第193条 – 盗品又は遺失物の回復
- 民法第194条 – 盗品又は遺失物の回復
- 民法第195条 – 動物の占有による権利の取得
- 民法第196条 – 占有者による費用の償還請求
- 民法第197条 – 占有の訴え
- 民法第198条 – 占有保持の訴え
- 民法第199条 – 占有保全の訴え
- 民法第200条 – 占有回収の訴え
- 民法第201条 – 占有の訴えの提起期間
- 民法第202条 – 本権の訴えとの関係
- 占有権の消滅
- 民法第205条 – 準占有
- 所有権
- 所有権の限界
- 所有権の内容及び範囲
- 相隣関係
- 民法第209条 – 隣地の使用
- 民法第210条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第211条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第212条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第213条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第213条の2 – 継続的給付を受けるための設備の設置権等
- 民法第213条の3 – 継続的給付を受けるための設備の設置権等
- 民法第214条 – 自然水流に対する妨害の禁止
- 民法第215条 – 水流の障害の除去
- 民法第216条 – 水流に関する工作物の修繕等
- 民法第217条 – 費用の負担についての慣習
- 民法第218条 – 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
- 民法第219条 – 水流の変更
- 民法第220条 – 排水のための低地の通水
- 民法第221条 – 通水用工作物の使用
- 民法第222条 – 堰の設置及び使用
- 民法第223条 – 境界標の設置
- 民法第224条 – 境界標の設置及び保存の費用
- 民法第225条 – 囲障の設置
- 民法第226条 – 囲障の設置及び保存の費用
- 民法第227条 – 相隣者の一人による囲障の設置
- 民法第228条 – 囲障の設置等に関する慣習
- 民法第229条 – 境界標等の共有の推定
- 民法第230条 – 境界標等の共有の推定
- 民法第231条 – 共有の障壁の高さを増す工事
- 民法第232条 – 共有の障壁の高さを増す工事
- 民法第233条 – 竹木の枝の切除及び根の切取り
- 民法第234条 – 境界線付近の建築の制限
- 民法第235条 – 境界線付近の建築の制限
- 民法第236条 – 境界線付近の建築に関する慣習
- 民法第237条 – 境界線付近の掘削の制限
- 民法第238条 – 境界線付近の掘削に関する注意義務
- 所有権の取得
- 共有
- 民法第249条 – 共有物の使用
- 民法第250条 – 共有持分の割合の推定
- 民法第251条 – 共有物の変更
- 民法第252条 – 共有物の管理
- 民法第252条の2 – 共有物の管理者
- 民法第253条 – 共有物に関する負担
- 民法第254条 – 共有物についての債権
- 民法第255条 – 持分の放棄及び共有者の死亡
- 民法第256条 – 共有物の分割請求
- 民法第257条 – 共有物の分割請求
- 民法第258条 – 裁判による共有物の分割
- 民法第258条の2 – 裁判による共有物の分割
- 民法第259条 – 共有に関する債権の弁済
- 民法第260条 – 共有物の分割への参加
- 民法第261条 – 分割における共有者の担保責任
- 民法第262条 – 共有物に関する証書
- 民法第262条の2 – 所在等不明共有者の持分の取得
- 民法第262条の3 – 所在等不明共有者の持分の譲渡
- 民法第263条 – 共有の性質を有する入会権
- 民法第264条 – 準共有
- 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
- 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令
- 所有権の限界
- 地上権
- 永小作権
- 地役権
- 民法第280条 – 地役権の内容
- 民法第281条 – 地役権の付従性
- 民法第282条 – 地役権の不可分性
- 民法第283条 – 地役権の時効取得
- 民法第284条 – 地役権の時効取得
- 民法第285条 – 用水地役権
- 民法第286条 – 承役地の所有者の工作物の設置義務等
- 民法第287条 – 承役地の所有者の工作物の設置義務等
- 民法第288条 – 承役地の所有者の工作物の使用
- 民法第289条 – 承役地の時効取得による地役権の消滅
- 民法第290条 – 承役地の時効取得による地役権の消滅
- 民法第291条 – 地役権の消滅時効
- 民法第292条 – 地役権の消滅時効
- 民法第293条 – 地役権の消滅時効
- 民法第294条 – 共有の性質を有しない入会権
- 留置権
- 先取特権
- 総則
- 先取特権の種類
- 一般の先取特権
- 動産の先取特権
- 民法第311条 – 動産の先取特権
- 民法第312条 – 不動産賃貸の先取特権
- 民法第313条 – 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
- 民法第314条 – 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
- 民法第315条 – 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
- 民法第316条 – 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
- 民法第317条 – 旅館宿泊の先取特権
- 民法第318条 – 運輸の先取特権
- 民法第319条 – 即時取得の規定の準用
- 民法第320条 – 動産保存の先取特権
- 民法第321条 – 動産売買の先取特権
- 民法第322条 – 種苗又は肥料の供給の先取特権
- 民法第323条 – 農業労務の先取特権
- 民法第324条 – 工業労務の先取特権
- 不動産の先取特権
- 先取特権の順位
- 先取特権の効力
- 質権
- 抵当権
- 総則
- 抵当権の効力
- 民法第373条 – 抵当権の順位
- 民法第374条 – 抵当権の順位の変更
- 民法第375条 – 抵当権の被担保債権の範囲
- 民法第376条 – 抵当権の処分
- 民法第377条 – 抵当権の処分の対抗要件
- 民法第378条 – 代価弁済
- 民法第379条 – 抵当権消滅請求
- 民法第380条 – 抵当権消滅請求
- 民法第381条 – 抵当権消滅請求
- 民法第382条 – 抵当権消滅請求の時期
- 民法第383条 – 抵当権消滅請求の手続
- 民法第384条 – 債権者のみなし承諾
- 民法第385条 – 競売の申立ての通知
- 民法第386条 – 抵当権消滅請求の効果
- 民法第387条 – 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力
- 民法第388条 – 法定地上権
- 民法第389条 – 抵当地の上の建物の競売
- 民法第390条 – 抵当不動産の第三取得者による買受け
- 民法第391条 – 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求
- 民法第392条 – 共同抵当における代価の配当
- 民法第393条 – 共同抵当における代位の付記登記
- 民法第394条 – 抵当不動産以外の財産からの弁済
- 民法第395条 – 抵当建物使用者の引渡しの猶予
- 抵当権の消滅
- 根抵当
- 民法第398条の2 – 根抵当権
- 民法第398条の3 – 根抵当権の被担保債権の範囲
- 民法第398条の4 – 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更
- 民法第398条の5 – 根抵当権の極度額の変更
- 民法第398条の6 – 根抵当権の元本確定期日の定め
- 民法第398条の7 – 根抵当権の被担保債権の譲渡等
- 民法第398条の8 – 根抵当権者又は債務者の相続
- 民法第398条の9 – 根抵当権者又は債務者の合併
- 民法第398条の10 – 根抵当権者又は債務者の会社分割
- 民法第398条の11 – 根抵当権の処分
- 民法第398条の12 – 根抵当権の譲渡
- 民法第398条の13 – 根抵当権の一部譲渡
- 民法第398条の14 – 根抵当権の共有
- 民法第398条の15 – 抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡
- 民法第398条の16 – 共同根抵当
- 民法第398条の17 – 共同根抵当の変更等
- 民法第398条の18 – 累積根抵当
- 民法第398条の19 – 根抵当権の元本の確定請求
- 民法第398条の20 – 根抵当権の元本の確定事由
- 民法第398条の21 – 根抵当権の極度額の減額請求
- 民法第398条の22 – 根抵当権の消滅請求
- 占有権
- 債権
- 総則
- 債権の目的
- 債権の効力
- 債務不履行の責任等
- 債権者代位権
- 詐害行為取消権
- 民法第424条 – 詐害行為取消請求
- 民法第424条の2 – 相当の対価を得てした財産の処分行為の特則
- 民法第424条の3 – 特定の債権者に対する担保の供与等の特則
- 民法第424条の4 – 過大な代物弁済等の特則
- 民法第424条の5 – 転得者に対する詐害行為取消請求
- 民法第424条の6 – 財産の返還又は価額の償還の請求
- 民法第424条の7 – 被告及び訴訟告知
- 民法第424条の8 – 詐害行為の取消しの範囲
- 民法第424条の9 – 債権者への支払又は引渡し
- 民法第425条 – 認容判決の効力が及ぶ者の範囲
- 民法第425条の2 – 債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利
- 民法第425条の3 – 受益者の債権の回復
- 民法第425条の4 – 詐害行為取消請求を受けた転得者の権利
- 民法第426条 – 詐害行為取消権の期間の制限
- 多数当事者の債権及び債務
- 総則
- 不可分債権及び不可分債務
- 連帯債権
- 連帯債務
- 保証債務
- 総則
- 民法第446条 – 保証人の責任等
- 民法第447条 – 保証債務の範囲
- 民法第448条 – 保証人の負担と主たる債務の目的又は態様
- 民法第449条 – 取り消すことができる債務の保証
- 民法第450条 – 保証人の要件
- 民法第451条 – 他の担保の供与
- 民法第452条 – 催告の抗弁
- 民法第453条 – 検索の抗弁
- 民法第454条 – 連帯保証の場合の特則
- 民法第455条 – 催告の抗弁及び検索の抗弁の効果
- 民法第456条 – 数人の保証人がある場合
- 民法第457条 – 主たる債務者について生じた事由の効力
- 民法第458条 – 連帯保証人について生じた事由の効力
- 民法第458条の2 – 主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務
- 民法第458条の3 – 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務
- 民法第459条 – 委託を受けた保証人の求償権
- 民法第459条の2 – 委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権
- 民法第460条 – 委託を受けた保証人の事前の求償権
- 民法第461条 – 主たる債務者が保証人に対して償還をする場合
- 民法第462条 – 委託を受けない保証人の求償権
- 民法第463条 – 通知を怠った保証人の求償の制限等
- 民法第464条 – 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権
- 民法第465条 – 共同保証人間の求償権
- 個人根保証契約
- 事業に係る債務についての保証契約の特則
- 総則
- 債権の譲渡
- 債務の引受け
- 債権の消滅
- 弁済
- 総則
- 民法第473条 – 弁済
- 民法第474条 – 第三者の弁済
- 民法第475条 – 弁済として引き渡した物の取戻し
- 民法第476条 – 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力
- 民法第477条 – 預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済
- 民法第478条 – 受領権者としての外観を有する者に対する弁済
- 民法第479条 – 受領権者以外の者に対する弁済
- 民法第481条 – 差押えを受けた債権の第三債務者の弁済
- 民法第482条 – 代物弁済
- 民法第483条 – 特定物の現状による引渡し
- 民法第484条 – 弁済の場所及び時間
- 民法第485条 – 弁済の費用
- 民法第486条 – 受取証書の交付請求等
- 民法第487条 – 債権証書の返還請求
- 民法第488条 – 同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当
- 民法第489条 – 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当
- 民法第490条 – 合意による弁済の充当
- 民法第491条 – 数個の給付をすべき場合の充当
- 民法第492条 – 弁済の提供の効果
- 民法第493条 – 弁済の提供の方法
- 弁済の目的物の供託
- 弁済による代位
- 総則
- 相殺
- 更改
- 民法第519条 – 免除
- 民法第520条 – 混同
- 弁済
- 契約
- 総則
- 民法第521条 – 契約の締結及び内容の自由
- 民法第522条 – 契約の成立と方式
- 民法第523条 – 承諾の期間の定めのある申込み
- 民法第524条 – 遅延した承諾の効力
- 民法第525条 – 承諾の期間の定めのない申込み
- 民法第526条 – 申込者の死亡等
- 民法第527条 – 承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期
- 民法第528条 – 申込みに変更を加えた承諾
- 民法第529条 – 懸賞広告
- 民法第529条の2 – 指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告
- 民法第529条の3 – 指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告
- 民法第530条 – 懸賞広告の撤回の方法
- 民法第531条 – 懸賞広告の報酬を受ける権利
- 民法第532条 – 優等懸賞広告
- 民法第533条 – 同時履行の抗弁
- 民法第536条 – 債務者の危険負担等
- 民法第537条 – 第三者のためにする契約
- 民法第538条 – 第三者の権利の確定
- 民法第539条 – 債務者の抗弁
- 民法第539条の2 – 契約上の地位の移転
- 民法第540条 – 解除権の行使
- 民法第541条 – 催告による解除
- 民法第542条 – 催告によらない解除
- 民法第543条 – 債権者の責に帰すべき事由による場合
- 民法第544条 – 解除権の不可分性
- 民法第545条 – 解除の効果
- 民法第546条 – 契約の解除と同時履行
- 民法第547条 – 催告による解除権の消滅
- 民法第548条 – 解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅
- 民法第548条の2 – 定型約款の合意
- 民法第548条の3 – 定型約款の内容の開示
- 民法第548条の4 – 定型約款の変更
- 贈与
- 売買
- 民法第555条 – 売買
- 民法第556条 – 売買の一方の予約
- 民法第557条 – 手付
- 民法第558条 – 売買契約に関する費用
- 民法第559条 – 有償契約への準用
- 民法第560条 – 権利移転の対抗要件に係る売主の義務
- 民法第561条 – 他人の権利の売買における売主の義務
- 民法第562条 – 買主の追完請求権
- 民法第563条 – 買主の代金減額請求権
- 民法第564条 – 買主の損害賠償請求及び解除権の行使
- 民法第565条 – 移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任
- 民法第566条 – 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
- 民法第567条 – 目的物の滅失等についての危険の移転
- 民法第568条 – 競売における担保責任等
- 民法第569条 – 債権の売主の担保責任
- 民法第570条 – 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求
- 民法第572条 – 担保責任を負わない旨の特約
- 民法第573条 – 代金の支払期限
- 民法第574条 – 代金の支払場所
- 民法第575条 – 果実の帰属及び代金の利息の支払
- 民法第576条 – 権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶
- 民法第577条 – 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶
- 民法第578条 – 売主による代金の供託の請求
- 民法第579条 – 買戻しの特約
- 民法第580条 – 買戻しの期間
- 民法第581条 – 買戻しの特約の対抗力
- 民法第582条 – 買戻権の代位行使
- 民法第583条 – 買戻しの実行
- 民法第584条 – 共有持分の買戻特約付売買
- 民法第585条 – 共有持分の買戻特約付売買
- 消費貸借
- 使用貸借
- 賃貸借
- 民法第601条 – 賃貸借
- 民法第602条 – 短期賃貸借
- 民法第603条 – 短期賃貸借の更新
- 民法第604条 – 賃貸借の存続期間
- 民法第605条 – 不動産賃貸借の対抗力
- 民法第605条の2 – 不動産の賃貸人たる地位の移転
- 民法第605条の3 – 合意による不動産の賃貸人たる地位の移転
- 民法第605条の4 – 不動産の賃借人による妨害の停止の請求等
- 民法第606条 – 賃貸人による修繕等
- 民法第607条 – 賃借人の意思に反する保存行為
- 民法第607条の2 – 賃借人による修繕
- 民法第608条 – 賃借人による費用の償還請求
- 民法第609条 – 減収による賃料の減額請求
- 民法第610条 – 減収による解除
- 民法第611条 – 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等
- 民法第612条 – 賃借権の譲渡及び転貸の制限
- 民法第613条 – 転貸の効果
- 民法第614条 – 賃料の支払時期
- 民法第615条 – 賃借人の通知義務
- 民法第616条 – 賃借人による使用及び収益
- 民法第616条の2 – 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了
- 民法第617条 – 期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ
- 民法第618条 – 期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保
- 民法第619条 – 賃貸借の更新の推定等
- 民法第620条 – 賃貸借の解除の効力
- 民法第621条 – 賃借人の原状回復義務
- 民法第622条 – 使用貸借の規定の準用
- 民法第622条の2 – 敷金
- 請負
- 委任
- 民法第643条 – 委任
- 民法第644条 – 受任者の注意義務
- 民法第644条の2 – 復受任者の選任
- 民法第645条 – 受任者による報告
- 民法第646条 – 受任者による受取物の引渡し等
- 民法第647条 – 受任者の金銭の消費についての責任
- 民法第648条 – 受任者の報酬
- 民法第648条の2 – 成果等に対する報酬
- 民法第649条 – 委任者による費用の前払請求
- 民法第650条 – 受任者による費用等の償還請求等
- 民法第651条 – 委任の解除
- 民法第652条 – 委任の解除の効力
- 民法第653条 – 委任の終了事由
- 民法第654条 – 委任の終了後の処分
- 民法第655条 – 委任の終了の対抗要件
- 民法第656条 – 準委任
- 寄託
- 組合
- 民法第667条 – 組合契約
- 民法第667条の2 – 他の組合員の債務不履行
- 民法第667条の3 – 組合員の一人についての意思表示の無効等
- 民法第668条 – 組合財産の共有
- 民法第669条 – 金銭出資の不履行の責任
- 民法第670条 – 業務の決定及び執行の方法
- 民法第670条の2 – 組合の代理
- 民法第671条 – 委任の規定の準用
- 民法第672条 – 業務執行組合員の辞任及び解任
- 民法第673条 – 組合員の業務及び財産状況に関する検査
- 民法第674条 – 組合員の損益分配の割合
- 民法第675条 – 組合の債権者の権利の行使
- 民法第676条 – 組合員の持分の処分及び組合財産の分割
- 民法第677条 – 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止
- 民法第677条の2 – 組合員の加入
- 民法第678条 – 組合員の脱退
- 民法第679条 – 組合員の脱退
- 民法第680条 – 組合員の除名
- 民法第680条の2 – 脱退した組合員の責任等
- 民法第681条 – 脱退した組合員の持分の払戻し
- 民法第682条 – 組合の解散事由
- 民法第683条 – 組合の解散の請求
- 民法第684条 – 組合契約の解除の効力
- 民法第685条 – 組合の清算及び清算人の選任
- 民法第686条 – 清算人の業務の決定及び執行の方法
- 民法第687条 – 組合員である清算人の辞任及び解任
- 民法第688条 – 清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法
- 総則
- 総則
- 相続
- 総則
- 相続人
- 相続の効力
- 総則
- 相続分
- 遺産の分割
- 民法第906条 – 遺産の分割の基準
- 民法第906条の2 – 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
- 民法第907条 – 遺産の分割の協議又は審判
- 民法第908条 – 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
- 民法第909条 – 遺産の分割の効力
- 民法第909条の2 – 遺産の分割前における預貯金債権の行使
- 民法第910条 – 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権
- 民法第911条 – 共同相続人間の担保責任
- 民法第912条 – 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任
- 民法第913条 – 資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担
- 民法第914条 – 遺言による担保責任の定め
- 相続の承認及び放棄
- 総則
- 相続の承認
- 単純承認
- 限定承認
- 民法第922条 – 限定承認
- 民法第923条 – 共同相続人の限定承認
- 民法第924条 – 限定承認の方式
- 民法第925条 – 限定承認の方式
- 民法第926条 – 限定承認者による管理
- 民法第927条 – 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
- 民法第928条 – 公告期間満了前の弁済の拒絶
- 民法第929条 – 公告期間満了後の弁済
- 民法第930条 – 期限前の債務等の弁済
- 民法第931条 – 受遺者に対する弁済
- 民法第932条 – 弁済のための相続財産の換価
- 民法第933条 – 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加
- 民法第934条 – 不当な弁済をした限定承認者の責任等
- 民法第935条 – 公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者
- 民法第936条 – 相続人が数人ある場合の相続財産の清算人
- 民法第937条 – 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者
- 相続の放棄
- 財産分離
- 相続人の不存在
- 遺言
- 総則
- 遺言の方式
- 遺言の効力
- 民法第985条 – 遺言の効力の発生時期
- 民法第986条 – 遺贈の放棄
- 民法第987条 – 受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告
- 民法第988条 – 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄
- 民法第989条 – 遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し
- 民法第990条 – 包括受遺者の権利義務
- 民法第991条 – 受遺者による担保の請求
- 民法第992条 – 受遺者による果実の取得
- 民法第993条 – 遺贈義務者による費用の償還請求
- 民法第994条 – 受遺者の死亡による遺贈の失効
- 民法第995条 – 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属
- 民法第996条 – 相続財産に属しない権利の遺贈
- 民法第997条 – 相続財産に属しない権利の遺贈
- 民法第998条 – 遺贈義務者の引渡義務
- 民法第999条 – 遺贈の物上代位
- 民法第1001条 – 債権の遺贈の物上代位
- 民法第1002条 – 負担付遺贈
- 民法第1003条 – 負担付遺贈の受遺者の免責
- 遺言の執行
- 民法第1004条 – 遺言書の検認
- 民法第1005条 – 過料
- 民法第1006条 – 遺言執行者の指定
- 民法第1007条 – 遺言執行者の任務の開始
- 民法第1008条 – 遺言執行者に対する就職の催告
- 民法第1009条 – 遺言執行者の欠格事由
- 民法第1010条 – 遺言執行者の選任
- 民法第1011条 – 相続財産の目録の作成
- 民法第1012条 – 遺言執行者の権利義務
- 民法第1013条 – 遺言の執行の妨害行為の禁止
- 民法第1014条 – 特定財産に関する遺言の執行
- 民法第1015条 – 遺言執行者の行為の効果
- 民法第1016条 – 遺言執行者の復任権
- 民法第1017条 – 遺言執行者が数人ある場合の任務の執行
- 民法第1018条 – 遺言執行者の報酬
- 民法第1019条 – 遺言執行者の解任及び辞任
- 民法第1020条 – 委任の規定の準用
- 民法第1021条 – 遺言の執行に関する費用の負担
- 遺言の撤回及び取消し
- 配偶者の居住の権利
- 遺留分
- 民法第1050条 – 特別の寄与
- 総則
- 相続の基礎知識
- 民事訴訟の流れ